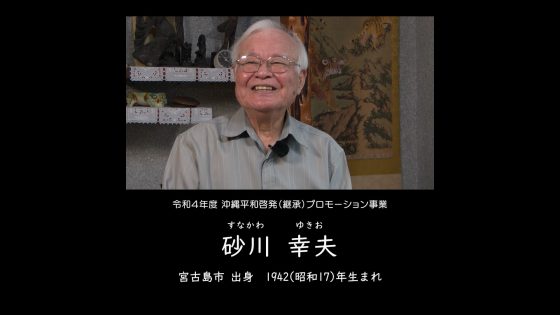戦後沖縄の美術教育
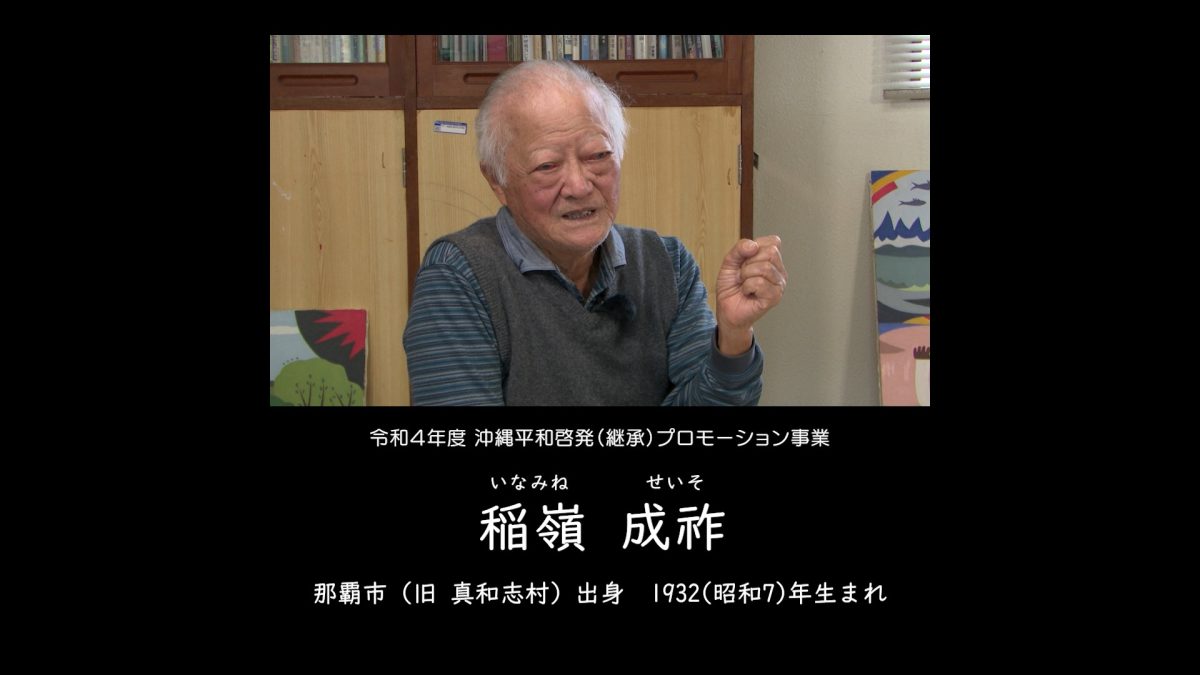

- 1932(昭和7)年生まれ
- 稲嶺 成祚さん(いなみね せいそ)
TIMELINE関連年表
| 1937 |
旧真和志村上之屋(現・那覇市)に生まれる。
|
|
|---|---|---|
| 1944 |
小学校6年時に、妹とともに学童疎開で熊本へ。船は対馬丸と同じ船団だった。
|
|
| 1946 |
疎開先の熊本から沖縄に戻り、両親とともに久米島で生活。
|
|
| 1947 |
4月、久米島高校に入学。5月、父の転勤により糸満高校へ転校。10月、新設の那覇高校へ通い、美術クラブに入部。
|
|
| 1955 |
琉球大学文理学部美術工芸科卒業。その後、東京の新宿美術研究所で学ぶ。
|
|
| 1956 |
美術教師として那覇中学校に勤務。以後、東中学校、浦添中学校などに勤務。
|
|
| 1972 |
琉球大学教育学部の教員として採用される
|
|
| 1983 |
琉球大学教育学部教授
|
|
| 1992 |
沖縄県造形教育連盟会長(~2001年5月)
|
|
| 2018 |
沖縄県文化功労者表彰受賞
|
STORY証言
証言者略歴
大学教授や沖縄県造形連盟会長として後進の指導にあたり、戦後の美術教育に尽力。画家としても長年にわたって制作・発表を行い、多くの賞を受賞している。
戦後の沖縄が復興していく様子や人々の生活、戦後の学校生活、美術活動、ニシムイ(美術村)などにも詳しい。
疎開先から故郷の沖縄へ
疎開先から沖縄に戻る
「沖縄に着いた。もう那覇が見えるよ」と言われ、甲板に上がってみたら(船から見えた沖縄の土地は)もう真っ白でした。やんばる辺りなら(土地は一面)緑に見えたかも知れません。那覇に近づいて、見た時には(沖縄の土地は)真っ白でした。島全部が皮を剝がされたみたいで、びっくりしました。那覇の港に着いたら、みんな船から下ろされて、その時に初めて黒人を見たので私はそれにも驚きました。彼らが子どもたちを一人ずつ(消毒していました) 。虫を殺すためのDDTという真っ白な薬、それを一掴み取ってズボンのベルトを緩めさせてそこにバーッと撒いたり、首元に入れたり、頭にもかけてもみ込んだりして(消毒していました)。DDTをかけ終わると、トラックにみんな乗せるわけです。「はい、行きなさい」というかたちで(乗せられました)。トラックの行き先は、インヌミヤードゥイ(引揚民収容所)ともう一つ、久場崎(の引揚民収容所)だったか、もう一つあったと思うけれど、そこにその日のうちに行くわけです。そこで迎える人がいたら、その人に引き取らせる。迎える人がいなければ、その場所が仮の宿泊場所になっていたと思います。僕の場合ちょうど叔父が来て、すぐに引き取ってくれました。
あの頃、叔父は石川に住んでいたので、(僕も)そこに行きました。(戦中は) 比屋定小学校の校長だった父と、母は久米島にいました。那覇にいたのは、僕の祖父母でした。十・十空襲で家が焼かれてしまい、天久にあった知人の一軒家を借りて住んでいたみたいです。僕には兄貴が一人いて、一中生(県立第一中学校生)でした。彼は一中生とともに(学徒隊として)戦死しています。本島の上之屋にいた5名の(家族の)うち、僕と妹は学童疎開をして、やんばるに逃げた祖父は生き延びて、祖母は病気で、兄は戦争で亡くなっています。僕は叔父に引き取られた後、叔父の手配で石川から移動できました。糸満から出る久米島行きの船に乗って、僕と妹は両親の元へ行きました。
戦後の教育環境と高校生活
久米島高校へ入学 その後 糸満高校へ
父が比屋定小学校の校長宿舎にいたので、そこで両親や妹と一緒に暮らしました。これで生きている家族は揃いました。当時の学校には初等科8年生までありました。初等科7年生と8年生は高校受験ができたので、(僕は)久米島高校を受験しました。当時の久米島高校は糸満高校の分校で、1・ 2学年までが久米島にあって、3年生からは本校の糸満高校に行くようになっていました。だから、学校の帽子や徽章などは、みんな糸満高校と同じものでした。父が(小禄の)高良小学校の校長になったので、僕らも小禄に住むことになりました。僕は転校するために糸満に行って、糸満高校を探していました。糸満高校生がいたので「糸満高校はどこですか」と尋ねたら、「お前は、馬鹿にしているのか」と言われて、こっちは一瞬何だろうと思いました。「お前は糸満高校の帽子を被っていて、糸満高校の場所が分からないのか。学校は始まっているのに、何故分からないのか」と言われたので、「実は、久米島高校の生徒です」と僕は答えました。「糸満高校に転校することになって、手続きをしたいのです」と言うと、「ああそうか」と言って彼は教えてくれました。
その当時は、糸満高校、知念高校、首里高校、それから 宜野座か前原か分かりませんが(いくつか高校がありました)。(沖縄は地区に分けられ)知念地区や何々地区というように、米軍が(土地を)区切っていました。そこにひとつずつ高校を作ったようです。当時、那覇はまだ人が住めなかったので、那覇には(高校が)ありませんでした。そのあと那覇高校が戦前の天妃小学校跡にできて、それは(1947年)10月頃でした。
当時の学生生活
糸満と小禄は8㎞ほど離れていて、とにかく大変な距離でした。(小禄の)赤嶺あたりには「MPハウス」というのがあって、米軍の軍用トラックが糸満にいる軍作業員を那覇に連れて来るために、朝は空のトラックが次々と糸満に行きました。そして糸満で軍作業員を乗せて、那覇に連れて来ました。朝、そのトラックは空っぽだから、みんなそれに便乗して糸満に行きました。トラック通学でした。帰りは、トラックが糸満で軍作業員を降ろし、空車の状態で那覇に帰るので、それにまた乗せてもらって小禄まで帰りました。糸満高校ではテントの校舎で、もちろん机や腰掛は無いので、自分でそうめん箱みたいな物を見つけてきてそれに座りました。机もないので、画板を首から下げて(机代わりにして)書いていました。
新設の那覇高校へ
あの頃、那覇の街はみんな焼野原でした。今の崇元寺あたりから(街中を)見ると、天妃小学校や上山中学校の建物は見えて、他には何にもないという感じでした(それが当時の那覇でした)。(学校でも)制服はなかったので、米軍の払い下げ(の服)を、みんな適当に着けていました。帽子も指定はなかったけれど、各々持っている帽子をみんなさまざまに被りました。白線を2本巻いた帽子と徽章は付ける。それだけは共通していました。あとは、全部それぞれ適当なもので(間に合わせていました)。革靴も米軍の(払い下げの)ものが結構ありましたが、ところが(サイズが)大きくて履けませんでした。小さな革靴が見つかったら、それこそ宝物でした。前が4~5センチも空くような靴しかないわけです。みんなそのような靴を履いていました。そのうちに下駄が流行りだして、2×4という(規格の)角材がありますが、それを切って下駄が作れました。だから、下駄を売るお店などもありました。男性も女性もみんな下駄ばかり履いていました。
美術クラブに入り美術の道へ
その頃 (高校生の進路は)お先真っ暗でした。当時は高校を出ても、軍作業員になる程度の選択肢しかなかった。その時に、島田寛平という美術の先生が「美術クラブを作るよ」と言うので、僕はあまり美術が好きとか得意でもなかったけれど、他にやる事がないから(美術クラブに)入りました。絵の具はないので、毎日鉛筆のスケッチだけをしていました。寛平先生は育て上手と言うか、ほめ上手だったので、みんな頑張っていました。当時はそのような様子で、僕らの後輩も含め那覇高校からは多くの美術家を輩出していました。母は、市場で古着などを「丸国マーケット」というのがあって、そこで古着を売ったりしていました。その時に、私は美術クラブにいたので、絵の具を買ってもらった記憶があります。それこそ (使う量は)大豆の大きさくらいで、少しずつ大事に絵の具を使っていました。(当時は)画用紙もないから、ゴミ捨て場に行って米軍の黄色い紙を(拾って来ました)。普通の薄い紙ではなく、画用紙のような黄色い紙で、よくそれに絵を描いていました。それから1年ぐらい経つと、画用紙が手に入るようになりました。その画用紙に絵を描くと、なぜか光って見えました。今まで(使っていた紙は)黄色で、最初から下地に色がついていたので、白い画用紙は描きにくいと思った記憶があります。
戦争の傷跡が残る地域での生活
父の転勤により転居 安里周辺の様子
(現在の那覇新都心)そこには、米軍の戦車があちこちにありました。キャタピラーが切れている戦車や、あるいは車体の真ん中が地雷などで爆破されて穴が空いている戦車とか、不発弾もたくさんありました。みんな芋畑で作業していると、不発弾が出てきました。それを字のクラブ、公民館みたいな屋敷に不発弾をみんな持ってきては、そこに積んでいました。(その場所は)僕の家の斜め向かいでした。人間の高さぐらいに(不発弾が)高く積み上げられていました。トラックの荷台いっぱいに、積めるぐらいの量になったら、誰かは知りませんが米軍に連絡して、(不発弾を)取りに来させていました。トラックで全部運んでも、暫くするとまた不発弾が増えていました。(不発弾が)目の前にいっぱいあっても誰も怖がりもしないよ。そんな生活でした。そこら辺で戦車(の残骸)が散らばっていました。そして (集落)後ろの那覇側の山を越えると、米軍の施設がありました。(そこには)黒人兵がたくさんいて、夜になると、女性を捕まえに(集落まで)よく来ていました。みんな、それが怖いので「黒人兵が来たよー」と言って知らせ、青年たちがみんなで口笛を吹きながら棒を持ったり、石を投げたりして追い払いました。
その頃、僕の家では父は校長をしていましたが、2×4の材木で下駄を作ったり、また、母は黒砂糖で飴玉を作ったりしていました。いわゆる、食えないものだから(副業で)そんな仕事もしていました。泡盛も売っていました。小さい店みたいなものを作って、ちょっとした商品を売っていました。
美術家を目指し大学へ
美術家を目指すことへの思い
沖縄は戦争のあとで社会的、経済的に疲弊していました。その中で、沖縄の復興のために力を尽くすということが、我々(若い世代)の将来の仕事であるという考え方がありました。ところが、絵描きになるということは、それから逃げているのです。だから、そういう意味では(僕は)負い目を感じていました。(一方で)良い絵さえ描けば、世間から認めてもらえると考えていました。僕は、琉大に美術工芸科を置いたアメリカのいわゆる司令部というか、(そのような)人たちのレベルが高かったという気がします。日本だったらおそらく芸術ではなく、まずは食べていける事を考えなさいと、経済的や社会的に(役立つ)実用的なものをつくるのであって、「美術工芸は何のためになるのか」と、(美術学科は)作らなかったと僕は思う。それをよく作ったと思うよ、アメリカは。
琉球大学の美術工芸科へ
僕は「絵を描くのに学問は要らない」と最初は考えていたので、琉大には行かないつもりでした。ところが、父は「ちゃんと大学に入って教員免許を取りなさい」と(言いました)。教員になる、ならないは別として、とにかく、そういうことをやれと。(父親の意見に)僕もそれほど反対せずに、「教える所があるのならそうしよう」と思い、また、習いたい気持ちもあったので(琉球大学に)入ったのです。
入学したけれど美術の授業では、立方体を毎日描かせるだけでした。石膏像もなく、画用紙に鉛筆で描くだけで、高等学校と何も変わりませんでした。そして、1学期の末ごろにカッパービーナス胸像が入ってきた。それも、あっちこっち虫が食ったように、へこんだりしていたけれど、学生はもう大喜びでした。石膏像も初めて見るようなものでしたから、それを木炭で描くのですが、みんな、その経験もないわけです。暫くすると、どこかの会社が木炭などの画材を売るようになっていました。「細長い木炭で 絵を描く方法があるのか」と(その時に知りました)。一般的な(家庭の)経済状況では、子どもを東京に進学させるのは難しいので、沖縄にいて、高校卒業後すぐに軍作業に行かせるよりも、勉強させるとしたら琉大に行くしかないのです。(授業のレベルは)相当低かったと思います、教科書もないし。高校の勉強の延長のようで、美術の授業だってスライドもないから、先生が教科書を開きながら色について講義をするけれど、先生の本には、申し訳程度の白黒写真が載っているくらいでした。授業としては理屈だけは聞こえるけれど、絵に対する感動は受ける側が想像するだけで、実際はわかりませんでした。
ニシムイ美術村の画家たちに学ぶ
あの頃、 (ニシムイ美術村の)先生方の家によく行っていました。後輩の翁長自修が玉那覇(正吉)さんの家によく行っていたので、僕もついていきました。今考えると (美術に関する)情報が何もないから、先生方が若い頃はどうだったのか、いっぱい話を聞きたかったのです。美術書がいっぱい来るわけでもなかったので、どんな勉強したのかいろんな話を聞くために、先生方の所に行く人はあの頃多かったです。(僕も)翁長自修と一緒に、よく玉那覇さんの所に行きました。だから、つまり日本本土の美術界の情報というのは、先生方を通して知る以外、方法はありませんでした。
東京の美術研究所で1年間学ぶ
東京では「新宿美術研究所」という所に通っていました。そこで、裸婦なんかもデッサンしていました。今の歌舞伎町の場所から入ってすぐの所に「新宿美術研究所」がありました。「日本アンデパンダン」という共産党がやっているアンデパンダン展があって、(僕は)それに小さい絵を2点出しましたが、その絵が良い悪いではなく、(僕は)その頃からヨーロッパやアメリカの流行を追うのではなく、日本独自の絵を作るべきではないか、という発想をするようになりました。日本アンデパンダン展に出した絵は、今はもうないけれど、陰影をなくした平べったい絵を描いた記憶があります。(僕が描く)今のような絵の原点のような作品でした。
教員と画家の二足のわらじ
教員と画家の二足のわらじ
あの頃は、忙しくて (夕方)5時には家に帰れませんでした。(帰宅は)いつも6時頃でした。家に帰ってご飯を食べた後、9時近くになってから2時間ぐらいは絵を描こうと決めていました。午後9時以降、11時までは絵を描こうと(決めて)続けていました。やっぱり「自分は絵描きになろう」と思ったのだから、そのためには9時以降の時間は、みんなそれに使おうと思いました。(僕の作品は実物を見ずに)想像して、勝手に描く絵だから描き続けられる。写実的な絵の延長としてやっていたら、写実的な絵は(仕事が終わって)夜に描けなくもないが、色も見えにくいし影ばかりなってしまう。しかも、あの頃の照明は今と違って、絵具の色も少し違って見えたかも知れないし、いわゆるリアリズムの絵を描く人は、夜に絵は描きませんよ。僕の場合は、頭の中で考えたものを次々と描けばいいような絵で、夜も昼も(影響)ないから、出来たかもしれません。
中学校から高校そして大学の教官へ
(中学校教員時代は)交換教員という制度があり、那覇地区から別の地区に出て、2年間勤務後に帰ってくる制度です。(前任校の)那覇中学校に、また戻らないといけなかったけれど、僕は那覇地区で一番小さい学校に行きたかったので、一番小さい学校はどこかと聞くと浦添中学校でした。「浦添中にお願いします」といって、そこに赴任したわけです。(学校では)校長先生がいつも校長講話をやりますが、その講話の中で「一生懸命勉強して、ドライバーや通訳になりなさい」という話をしていたので、「もう少し志が高い話をするべきでは」と思ったことがあります。
沖縄工業高校のデザイン科には、(教諭として)琉大の同期生で喜村朝貞という人がいたし、後輩の翁長自修がいたので、彼らから「工業高校に来ないか」と誘われました。(それで)僕は浦添中学校から沖縄工業高校のデザイン科に移りました。(当時は)デザイン科ができたばかりで、ある意味で未開拓の分野で、僕らが最初の学生だった那覇高校時代と同じように、「先生の力量次第で、生徒は育つ」という思いがして、先生方は想像力が試されるような授業をどんどんやりました。翁長自修さんが僕より2か年ほど先に、琉大から座学か何かを頼まれて彼が教えていました。そして、彼が1年ぐらい早く琉大に勤めるようになって、(僕も)彼と同じように琉大で座学を担当することになり、一般教養の美術関係の授業をしました。100名ぐらい来るから実習は出来ず、琉大では講義をしていました。
若い世代に伝えたいこと
若い世代に伝えたいこと
沖縄の独自性については、有るといえば有る、無いといえば無いのかもしれない。僕は、(沖縄は)独自性がある方だとは思う。言葉も違うし、習慣も東南アジア系の習慣が結構あるし、いろんなものが 違いますよね。(それは)良いことでもある。別に威張ることでもない。或いは悪びれることでもない。それでいいのではないかと思います。非常に大雑把に言えば、東南アジアや華僑などの影響を受けた日本の民族の一番の北限が、沖縄だと思います。そして、大和(日本)文化の南限が沖縄なのです。その2つが混ざっているという意味で、沖縄にはユニークなところがある。それは、別に威張ることもないけれど、落ち込むこともないと思います。それを認識する必要があるかもしれません。
作品作りに一番心がけていること
僕の場合は、まあ一番簡単に言えば「見て楽しい」、そんな絵を描きたい。見ていて「面白い」「楽しい」という絵を描きたい。これがまず基本としてあります。そのうえで「どんな絵を描くか」となりますが、月日が経ち、ずっと後になって気がついたことですが、日本の絵描きがパリやニューヨークに行ったりして向こうで流行っているものを学んできて、「パリではこんな絵を描いていた」と言って、(例えば)そのまねをするのです。それは 「創造をする」ということとは違うと思います。つまり、外国で流行っていない物を作らないといけない。例えば、パリでは見たことのない作品を日本でつくる。これが「創造」です。そうは言っても、 「創造」とは、ふわふわしたものを捕まえるみたいに簡単にできるものではなく、自分の根っこにある土壌のようなものだと思います。
安次嶺(金正)先生が言いました。「日本の造形は平面性だよ」と。この言葉が(記憶に)残っていて、首里城で例えると、一番長い横の面が正面で奥行きはあまりない。ところが、美術書に出てくる西洋の教会などの建物は縦長です。そのような例をあげて(先生は仰いました)。「日本の造形というのは平面性なのだよ」と。学生の頃だったら、「平面性は悪い」と解釈する傾向があったかもしれない。「立体的でないといけない」と。石膏デッサンでも何でも立体的に描くように教えられるから。「平面性はよくない」と、つい解釈してしまう。そうではなくて「平面線も立体性も同様に素晴らしい」。イーコール(同等)というか 「上下はない」という意識があって、自分の中にある平面性を上手に生かしながら、他所の国の流行ではなく、日本で良い物を作るべきではないだろうか」というふうに思って、今は描いているわけですね。